企業が効率的に節税を行いながら従業員の意欲を向上させる手段の一つとして、決算賞与が注目されています。本記事では、決算賞与の概要、節税効果、支給のメリットとデメリット、税務上の要件について詳しく解説します。これから決算賞与の導入を検討する企業にとって、必見の情報をまとめました。
決算賞与とは
決算賞与とは、夏や冬のボーナスとは異なり、年度の業績に応じて決算時期に支給される臨時の賞与を指します。業績が好調だった際に従業員に利益を還元する恩給的なボーナスで、支給額や実施の有無は企業ごとに異なります。
決算賞与の最大の特徴は、損金として計上できる点です。これにより法人税の課税所得を抑える効果が期待できます。ただし、税務上の要件を満たす必要があり、注意が求められます。
決算賞与のメリット
1. 法人税の節税効果
決算賞与は、損金として計上することで法人税の課税所得を減らすことが可能です。以下の例を挙げて説明します。
- 課税所得: 1,700万円
- 法人税率: 23.2%
- 決算賞与支給額: 500万円
支給しない場合の法人税額は、
一方で、500万円の決算賞与を支給した場合、課税所得は1,200万円となり、
結果として、法人税額は116万円節税できます。このように、決算賞与は税負担を大幅に軽減する手段となり得ます。
2. 従業員のモチベーション向上
決算賞与は従業員への利益還元として有効であり、企業に対する信頼感や仕事への意欲を高める効果があります。臨時ボーナスとして支給することで、従業員にとっての特別感があり、エンゲージメント向上に寄与します。
決算賞与のデメリット
1. 会社の資金減少
決算賞与を支給すると、節税額以上の資金が流出します。例えば、課税所得が2,000万円で税率が23.2%、決算賞与額が800万円の場合、節税額は約185万円ですが、会社の資金からは800万円が流出します。資金繰りへの影響を十分に考慮する必要があります。
2. 経理処理の負担増
決算賞与を支給する際は、所得税や社会保険料の計算、源泉徴収、支給手続きが必要となります。また、税務調査時の対応として、支給の実態を証明する書類の保管も欠かせません。
3. 継続期待のリスク
一度支給した場合、従業員が翌年度以降も支給を期待する可能性があります。業績次第で支給が難しい年には、逆にモチベーションが低下するリスクもあるため、基準の明確化が求められます。
税務上の要件
決算賞与を損金として計上するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります:
- 支給額の通知 支給する全従業員に対し、同時期に支給額を通知する必要があります。通知方法は書面が推奨され、記録を残すことが重要です。
- 1ヵ月以内の支給 決算日の翌日から1ヵ月以内に通知額を支給する必要があります。銀行振込を利用すると支給事実が証明しやすくなります。
- 当期の損金経理 当期中に未払金として経理処理を行い、損金計上する必要があります。
上記の要件を満たせない場合、支給した事業年度で損金計上することとなり、節税効果が得られなくなる可能性があります。
決算賞与を支給する際のポイント
- 資金繰りの確認 節税効果だけでなく、手元資金の減少を考慮し、資金繰りに支障が出ないか検討します。
- 従業員への説明 支給基準を明確にし、一時的なものである旨を従業員に説明します。
- 税務調査対策 書面による通知や銀行振込の記録を残すことで、税務調査に備えます。
まとめ
決算賞与は、節税効果と従業員のモチベーション向上というメリットを持つ一方で、会社の資金減少や経理負担増といったデメリットもあります。導入を検討する際は、節税効果だけでなく、資金繰りや従業員の期待管理など総合的な視点で判断することが重要です。
節税対策について詳しく知りたい場合や、決算賞与の導入を検討している方は、ぜひ専門家にご相談ください。無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
公式LINEのAIチャットで24時間ご質問にお答えしています!
有人対応時間:平日9時から17時

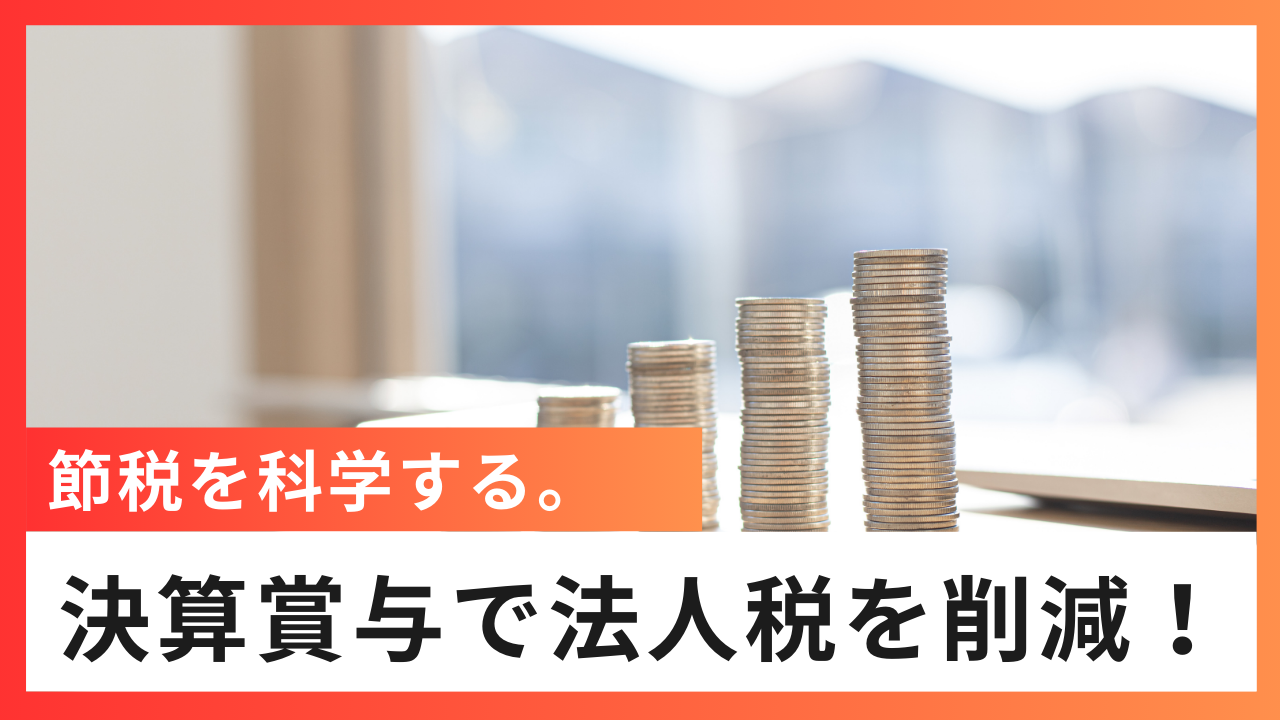
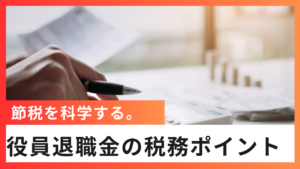


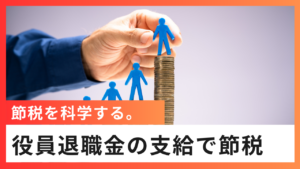
コメント